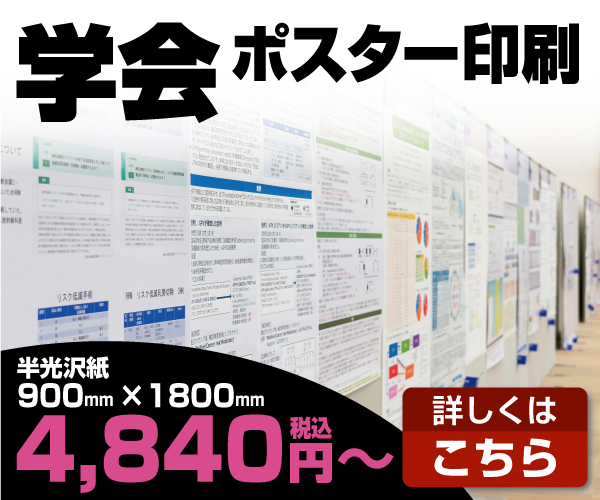外的妥当性とは?

外的妥当性とは?
『外的妥当性』(がいてきだとうせい、External Validity、仏語表記:Validité Externe)とは、研究結果が他の状況や集団にどの程度適用できるか、すなわちその結果が普遍的に適用可能かどうかを評価する概念です。外的妥当性が高い研究は、異なる環境や異なる集団にも適用できるため、結果がより一般化されやすいとされています。外的妥当性は、実験室での厳密な研究が現実世界でも同様に通用するかどうかを判断するために重要な指標です。
外的妥当性の歴史と由来
外的妥当性の概念は、20世紀中頃に心理学や社会科学の分野で発展しました。研究者は、実験結果が特定の環境や条件下でのみ適用できる場合、その結果を広範な文脈に一般化することが難しいと認識していました。この問題を解決するために、外的妥当性という考え方が導入されました。
アメリカの心理学者ドナルド・キャンベルとジュリアン・スタンレーが1963年に発表した「実験と準実験の設計」という著作で、外的妥当性の概念が広く認知されるようになりました。彼らは、研究結果の一般化を妨げる要因として「選択バイアス」や「実験効果」などを挙げ、これらの影響を最小限に抑える方法について議論しました。
外的妥当性の要素と重要性
外的妥当性を評価する際には、以下の要素が考慮されます:
- 集団妥当性: 研究で使用されたサンプルが、他の集団にも適用可能かどうかを評価します。例えば、特定の年齢層や文化圏のみに限定されたサンプルでは、その結果が他の集団にも当てはまるか疑問が残ります。
- 環境妥当性: 研究が行われた環境(実験室やフィールドなど)が、他の環境にも結果を適用できるかどうかを評価します。実験室で得られた結果が現実世界でも同様に適用できるかが焦点です。
- 時間妥当性: 研究が行われた時期や期間が、他の時期にも結果が適用できるかどうかを評価します。時間の経過とともに、社会や技術の変化が影響を与える可能性があるため、これも重要な要素です。
外的妥当性は、研究結果が特定の条件下でのみ有効であり、広範な状況や集団に適用できない場合、結果の一般化に限界が生じることを意味します。例えば、特定の地域や文化に限定された研究結果を、異なる文化圏に直接適用することは難しい場合があります。外的妥当性が高い研究は、異なる条件や集団においても同様の結果が得られる可能性が高いため、結果の信頼性が増します。
現在の使われ方と応用
現代の研究では、外的妥当性を高めるためにさまざまな工夫が行われています。例えば、異なる集団や環境で同様の研究を繰り返す「再現研究」は、外的妥当性を検証するための重要な手法です。また、メタ分析も外的妥当性を評価するために用いられ、異なる研究結果を統合することで、より一般化可能な結論を導き出すことができます。
さらに、異なる文化的背景を持つサンプルを使用した「クロスカルチュラル研究」も、外的妥当性を高めるために行われています。この方法では、同じ研究が異なる文化や国で行われ、その結果が一貫しているかどうかを確認します。これにより、結果の一般化がより確実なものとなります。
社会科学や行動科学、教育学、さらには医療や公衆衛生の分野でも、外的妥当性の評価は重要です。例えば、医療研究では、特定の薬が異なる年齢層や民族に対してどのように効果を発揮するかを評価するために、外的妥当性が考慮されます。
外的妥当性の概念は、研究者が結果を広範な状況に適用する際のリスクを評価し、科学的な知見がより広い文脈で信頼できるものとなるようにするための基盤を提供します。今後も、外的妥当性を考慮した研究が増え、科学的な発見がより多くの状況に適用可能な形で共有されることが期待されます。